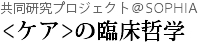2.
これまでの話はもっぱらケアする側の立場からのものでした。しかし、ケアは能動性と受動性の両側面をもつという点は、ケアされる側からしても重要だと思うのです。しかし、「ケアの哲学」にとってネックになるのは、「ケアされる側」は、「ケアする側」としての女性たちと同様に、ケアについての語り手であることが制限されてきた、ということです。もちろん、まだ、あるいはすでに発話が困難である場合が少なくないという事情もあるでしょうし、「私的」なこととして語るのがはばかられたというのもあるでしょう。しかし、「思いやり」のイメージに含まれる、ケアする側=能動的主体、ケアされる側=受動的客体、という非対称性が影を落としているように思えます。
そこで私が注目しているのは、「当事者研究」と呼ばれる実践です。「当事者研究」は、障害、病、その他の困難の当事者が、自らの体験や状態を専門家やワーカーによって受動的に説明されるのではなく、自分たちで研究していこうという実践です。この実践を行っている研究者の一人に、現在私が所属する東京大学グローバルCOE「共生のための国際哲学教育研究センター(UTCP)」共同研究員で、脳性まひ当事者の熊谷晋一郎さんがいます。彼の介助論は「ケアの哲学」に重大な示唆を与えていると思います。
身体障害者の介助において、ケアされる側は動きを指示する立場にあり、ケアする側は指示を受ける側になることがあります。障害者が介助者や事業所の都合に振り回されるのではなく、障害者が自由に自己決定するという、障害者自立生活運動の考えから「介助=手足論」と呼ばれるようになったモデルによれば、そうなります。つまり、能動的主体と受動的客体の関係がケアの通説とは異なりいわば逆向きになっているとも言えるわけです。そもそも、ケアする側=能動的主体、ケアされる側=受動的主体、という図式は必ずしも妥当でないのです。
ケアされる側とケアする側が運動の同志であった時代とは異なり、ケアが「労働」となった現在、薄給の労働に際して純然たる「道具」としてふるまうことのキツさは介助者たちから頻繁に聞こえてきます。しかし、それだけではありません。
熊谷さんが指摘しているのは、純然たる自己決定を追求しようとすると、実は、自由に行為できない、ということです。自己決定論を徹底するなら、被介助者は、たとえば、風呂に入るとき、腕から洗うか足から洗うか、右足から洗うか左足から洗うか、さらには、小指から洗うか親指から洗うか、まで指示を出すことになります。しかしそもそも、人が行為する時、このような自己決定をしているのか。普通、自由に行為していると言える時、たとえば歯磨きをしている場合、一挙手一投足には意識が向いておらず、むしろ、歯磨きをしながら午後の予定のことでも考えているはずです。
熊谷さんは、『リハビリの夜』という本の中で、〈介助者の身体を想像的に取り込んで「触れるように触れられる」〉という仕方で、力の源泉をどちらか一方に還元せずに「行為」を達成するありかたを記述しています。これは「介助=手足論」からの撤退ではなく、むしろ徹底だと思われます。というのも、道具とは、例えば、歯ブラシはそれを握る者がまったく意のままにできる存在ではなく、むしろ、使用者がそれの形状や重さに合わせてそれができることを促す場合にはじめて道具としての本領を発揮するはずだからです。現代の哲学は、すべてを自己決定しなくてはならないとすればまさに行為できないなることを「フレーム問題」として問題化し、そもそも、透明な意志が身体運動を引き起こすのが行為のモデルだとする「古典的意志理論」を批判することで行為論を展開してきました。当事者研究から学ぶことで、ケアの哲学は、哲学の周縁的存在ではなく、核心的な問題に入り込んでいることに気がつきます。
このリレーエッセイの第一回で、大橋先生は、「人間関係のシーソーが現実にはいつでも傾いていること、その傾きに気づいていることが、まさにケアということではないか」と、述べています。思いやりと重荷、能動性と受動性、人と人、これらはすべていつでも「シーソーの傾き」をもちこたえることで保たれている危うい存在でしょう。なぜシーソーは傾くのか。その理由を探究することで傾きが傾きすぎないようにすること、これが「ケアの哲学」の課題だと私は認識しています。あらゆる角度から、偏りなく、私たちの生の実相を照らし出すことができれば。これからも様々な方々と問題を共有し、かつ、解決のための知を結集したいと思っております。