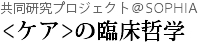1997年に介護保険法が制定されてから、介護の位置づけが措置から契約へと変わり、介護という社会資源はサービス業のひとつとして捉えられるようになった。しかし、これだけ高齢社会になっているにもかかわらず、自分や身内が当事者にならないかぎり、まだ介護の社会的位置づけが定着しているとは言い難い。急速に高齢社会が進行している日本において、また万人が必ず迎える日が来る老後と介護に対する理解は、今後の最重要課題と言えるだろう。
まず最初に考えたいことは、介護とは本当にサービス業というくくりで簡単に捉えていいものだろうか、ということである。当事者ではない人々や、介護現場を本当には知らない人々、マスコミや社会通念から考えると、残念ながら介護業界に対する評価はとても低いようである。それも特に介護業界の人材・サービスに対する評価が低い。つまり求めている側の要望と、与える側のサービスの質の差が大きいということである。
それでは、介護において求めている側の要望とは何だろうか。介護以外の他業種のサービス業において求められているものと比較してみたい。サービス業としての評価の高い企業として、某外資系のアミューズメントパークや某外資系の全国チェーンのカフェ、有名ホテルの接客などが思い浮かぶ。そこで行われているサービス業としての接客の教育の水準の高さを否定するつもりはない。見習うべきところが多いのも事実だろう。しかし、いずれの場合も、そこで利用者から求められているサービス内容は単純であり、困難なものではない。アミューズメントパークやカフェやホテルで利用者が求めているものは、ただ楽しむこと、ワクワクすること、気分転換、気晴らしである。簡単に言えば、彼らは遊ぶためにそこに来ているのである。そのような場面では、爽やかな笑顔、丁寧な言葉づかいと態度、快適さと優雅さを満たすためのちょっとした気遣いさえあれば、充分に質の高いサービスを提供したことになる。また利用者の側も、非日常の中で「あら、荷物で困っていたら、従業員がさっと手伝ってくれたわ」「この店はいつ来ても店員さんが感じが良いわ」「来客者がすぐに乗れるようにエレーベーターがいつも1階で待機している」「帰るときに従業員が総出で送ってくれて、姿が見えなくなるまで丁寧にお辞儀してくれた」というような程度のサービスで大満足であり、充分にこころが充たされるのである。
それに対して、介護において利用者が求めているものは何だろうか。それはずばり、「生活」そのものである。それも、自分ひとりや家族だけでは困難になりつつある、或いはまったく困難な「生活」である。「生活」とは毎日の食事や睡眠や排泄(心身機能・身体構造)であり、またその次が移動・運動、コミュニケーション、対人関係、家庭生活などのレベル(活動)であり、その次に、その人にとっての「人生」への「参加」である(主には、その人にとっての課題や行為の遂行を意味する)。(この3つの概念はレベルの差はなく、相互関係によって人が生きることの全体像を表すとして、2001年WHOがICF(国際生活機能分類)として定めている。)ここで分かるように「生活」とは、健康なときには無意識だった自分のからだそのものであり、知らない間に染みついた自分流のやり方(からだの洗い方、洗面の仕方、手の洗い方、料理法や味の好みに至るまで…)であり、口ぐせであり(自分流のコミュニケーションのとり方)、好きな人のタイプや人間関係のスタンス、ひいては人生に対する価値観そのものであったりもする。「生活」に関しては、夫婦や親子といった家族でさえ、長年暮らしていても100%不満がないということはない。それほど個人に密着したものなのである。
その「生活」が困難になったらどうなるだろう。一番分かりやすい例で言えば、健康なときには、どんなに親密な夫婦でさえ、個人の排泄の仕方を理解していることは稀である。それほど「生活」の根幹とも言える排泄機能などは個人のからだに密着したものである。「介護」という「サービス業」において求められているものとは、ずばり、そのような個人のからだに密着した排泄を代表とする、からだや人生に染みついた生き方のお手伝いなのである。