ケアは日々の暮らしの中に転がっている。いや「日々の暮らし」とは「ケアそのもの」だと言ってもいいかもしれない。英語の「care」という単語の用法をちょっと調べてみれば、いかにそれが「普段づかい」のことばであるか、すぐに分かるだろう。「take care of 」でおなじみの「大事にする」「世話をする」という意味はもちろんだが、面白いのは「注意、関心」や「心配、苦労」などといった、必ずしも何かに実際に「手を出す」ことよりも手前にある、意識や感情、欲求に関わる表現が多いことだ。ちょっと気になる、というところからケアは始まっているし、また相手の世話をしているつもりでも、実はケアとしては不適切な場合もある。つまりケアという言葉は、私たちの生活を形作る「意識」や「感情」や「行為」を繋ぐような、豊かな拡がりをもっているのである。
だが、日本語の中に入ってきた「ケア」という言葉は、なぜか随分狭い意味で使われ続けてきた。今でこそ「ケアマネ」とか「デイケア」とかいった、介護の領域での用法が広がって、福祉や医療の世界がイメージされるようになって来ているし、震災や事故、犯罪などの被害にあった人への「心のケア」が注目されるようになった。しかし十数年前まで、この国では「ケア」といったら、何をおいてもまずは「お肌のケア」「ヘアケア」「アフターケア」といった、化粧品などのCMに躍る「何となくやさしい、素敵な言葉」に過ぎなかったのである。
もちろん、その第一の理由は「ケア」の多義的な拡がりをそのままに訳し出せることばが、日本語には見つからないからである。しかし、それだけでもないような気もする。というのも、用法が多少は拡がってきた現在でも、私たちの「ケアへのイメージ」の根っこは、あまり変わっていないような気がするからだ。つまり「何となくやさしくする」のがケアなんだ、という感じ方である。
でも「やさしくすること」だけが「ケア」なのではない。ミルトン・メイヤロフが『ケアの本質』で言い当てたように、ケアすることは「相手の成長や自己実現を助ける」ような「ひとつの過程」としての関係性のありかたなのだ。相手にとって必要なものを探り、応えていこうとするならば、それは時にやさしく、時に厳しく、その姿は変わって当然なのである。
「ほめて育てる」という教育評論家のことばの「やさしさ」にも、一理ある。でも人がそれだけで「育つ」のではない。人が育つのは「かかわり」という「場の豊かさ」においてではないか。それは誰かが一方的に何かを「与える」ことではうまれない。大事なのはそこに「対話」という「やりとり」が交わされることだ。
ほめることを「与えるやさしさ」だとすれば、「受け入れるやさしさ」に当たるのは、耳を傾けることだろう。そして「ケア」の本当の入り口が、そこにある。(崎川)
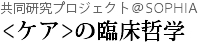
 名詞編
名詞編 動詞編
動詞編