日本人には握手という習慣がない。お辞儀という文化の深遠な美しさを否定しようというわけではないが、やはりそれは相手との距離を測り合う仕草であって、親密さを作り出す仕草ではないような気がして、なんとなく残念に思うことがある。
お辞儀はその角度や時間で意味を変えるが、握手にも、片手か両手か、どれくらいの間握っているか、などによって、様々な表情があるのは同様である。だが大きな違いは、じっさいに相手の身体に直に「ふれる」ということだろう。そしてそうやって手と手がつながった瞬間、私たちは時としてそこに「意外」な感触としての、他者の肌触りを知ることがある。
仰ぎ見るような人の手が弱々しかったり、小柄な人が驚くほど力強く、温かい握手をしてくれたり。ひんやりとした手、汗ばんだ手、などなど。いずれにしても私たちはそこで、肩書きとか、自分の思い込んでいた性格とかいった「言葉で記述できる情報」ではなく、「この感じ」としかいいようのない、なまのイメージにおいて相手に出会うのである。
それは同時に、身体としてある自分自身を、瞬間相手にゆだねることでもある。だから当然それは時として艶かしく、また恥じらいを伴うことでもあるだろうし、それゆえに「暴力」として感じられることさえある。しかし、そのように「他者に触れる」ことを通じて、私たちはお互いが身体という「感じやすさ=弱さ」を生きる存在であることを意識し、引き受けてゆくのではないだろうか。
お辞儀をする、ということの中では、そんな危うさは回避されていく。顔を伏せることは、相手を立てる「優しさ」であると同時に、自らの弱さの中に埋没して、それを「忘れること」でもあるのだ。繰り返される「謝罪会見」やら「土下座」やらを思い浮かべればよい。
でも、そうだからこそ、日本人だって肝心なときには必ず手を取り合ってきたのではないだろうか。子どもの手、恋人の手、夫婦の手、そしてお年寄りの手。思わず手を差し伸べて、相手に「ふれる」ところから、ケアは始まり、深まってゆく。(崎川)
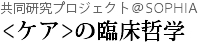
 名詞編
名詞編 動詞編
動詞編